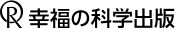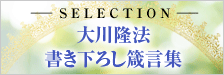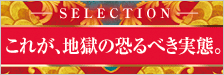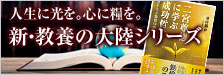2025年04月01日
【時事メルマガ】トランプ大統領が「男子の女子スポーツからの排除」と書かれた大統領令に署名
政治とは、この世の現象として現れてくる具体的な活動ですが、そのもとにあるものは、やはり、何といっても、政治哲学、理念、あるいは基本的なものの考え方や価値観です。そういうものが投影されて、現実の政治的な活動になってくるわけであり、その意味で、政治思想、政治哲学というものは非常に大事です。このバックボーンのところが、どういうものであるかによって、現実に現れてくる活動や行動が大きく変化してくるのです。
※以上『政治の理想について』より抜粋
▼ POINT ▼ クリックすると該当箇所へジャンプします。
● バイデン前政権とは正反対の立ち位置を示したトランプ政権
● 「LGBTQ」のQは、セクシャルマイノリティの団結を促す言葉
● 立ちはだかるトランスジェンダー女子の壁に苦悩する女子スポーツ選手たち
● LGBTQ推進派が脅かす「言論の自由」
● 日本の現政権の見解と、幸福の科学の教義から見る「LGBTQ」
● 絵本『王さまと王さま』に欠けている大局的な視点
● 今、読み返したい この一冊!
❚ 報道
トランプ大統領は、数十人の女性アスリートらが見守るなか、「男子の女子スポーツからの排除」と書かれた大統領令に署名。トランスジェンダー女性の女子スポーツ競技への参加を禁止した。「CNN 2025.2.06」
CNNの記事は、この署名に先立って、ホワイトハウスの当局者が「新しい教育改正法第9編(タイトルナイン)が、バイデン政権とは正反対の立ち位置となることを指摘した」と報じた。また、ホワイトハウスの報道官が「トランプ氏が国際オリンピック委員会(IOC)と全米大学体育協会(NCAA)が、男子の女子スポーツへの出場禁止を期待する」と述べたと報じ、こうした動きが強い圧力になるという懸念も併せて報道している。
❚ 「LGBTQ」のQは、セクシャルマイノリティの団結を促す言葉
一般的に「LGBT」と報じられている言葉だが、「LGB=レズ、ゲイ、バイセクシャル」というのは性的指向のことで、「T=トランスジェンダー(性自認)」とは大きく異なるものだ。最近は、Qが加えられ、自分がどちらの性か判らないという「Q=クエスチョン」、あるいは「Q=クィア(Queer)」の頭文字が使われている。クィアとはもともと「風変わりな」という同性愛者への侮蔑の言葉として使われていたが、それを逆手にとって、セクシャルマイノリティの団結を促す言葉として、今では肯定的に使われている。
❚ 立ちはだかるトランスジェンダー女子の壁に苦悩する女子スポーツ選手たち
バイデン前政権下において、政府関係の要職に、過去最多のLGBTQの人々が起用された。また、バイデン前大統領は退任前に「ソドミー規定」に基づく同性愛行為で有罪の元兵士ら約2,000人に恩赦を与えた。「ソドミー」というのは、旧約聖書に書かれた言葉で、自然に反した性愛のことだ。やがて、アメリカ民主党政権下で広がりを見せたLGBT政策を批判しようものなら、「トランス・フォビア(嫌悪)」とのレッテルを貼られてしまう。かつて、ウィンブルドン選手権で史上最多の優勝回数を誇るマルチナ・ナブラチロワ氏もその一人。自らレズビアンであることをカミングアウトする一方で、トランスジェンダーがスポーツの女子カテゴリーに参加することを不公平で、不正行為であると断言。その結果、各種団体から除名され、多額のスポンサー契約が解除されたという経緯もある。
アメリカのコネチカット州に住むセリーナさんは8歳から陸上を始め、短距離走者としてオリンピックでの金メダルの夢を抱いていた。しかし、トランスジェンダー女子の選手が上位を独占。必死で努力するもその壁を破ることができなかった。苦境に立たされている現状を動画で配信。日本の元陸上競技選手の為末大氏が、あまりの惨状に驚き、「公平性とジェンダーの自己決定は競技の場では対立する」と彼女を擁護した。
この行き過ぎたジェンダー志向が、今、アメリカの闇となって健全な社会を侵食しつつあるのだ。つまり、LGBTQに対して批判を加える勢力に対する恫喝行為が、「言論の自由」を脅かそうとしている。その象徴的な出来事が、日本で起こった。原題は『Irreversible Damage』。産経新聞出版から『トランスジェンダーになりたい少女たち』として翻訳出版されたが、実はこの本、一度はKADOKAWAから出版される予定だった。しかし、書店に放火するなど、さまざまな脅迫、嫌がらせ等によって焚書寸前になったのだ。全米ではベストセラーになり、タイムズ紙(ロンドン)、エコノミスト誌、サンデー・タイムズ誌らがこぞって「今年最高の一冊」と評された本であるにもかかわらず。
内容は、まだ精神状態が不安定な十代の少女たちが、大人へと向かう途上で、SNSやユーチューブ、学校の医療機関が煽るジェンダー指向、つまり、「君は実は男かも知れないよ」という誘惑によって翻弄される。そして、少女たちは男性へと変貌するために処方されるテストステロンという薬を服用。この薬は心臓病発作のリスクが従来の5倍に高まる。また、バストを目立たせないために着用するブレストバインダーは、血管やリンパ節などの損傷の危険が大きく、エスカレートすると乳房除去施術に到る例も少なくない。このように思春期の少女らが、精神的にも肉体的にも大きな痛手を負うことを真摯にレポートしている。
❚ 日本の現政権の見解と、幸福の科学の教義から見る「LGBTQ」
改めて、日本の現政権、石破総理のLGBTに関する公式見解を紹介する。「世の中にLGBTの方々が相当数いる。同性婚が認められないことで不利益を受けているとすれば、救済する道を考えるべきだ」。先頃、トランプ大統領は、3月7日に行われた上下院合同会議での演説で子どもたちに「あなたの神のつくりたもう体は、そのままで美しい」とメッセージを贈った。トランプ新政権下とは対極的となるLGBT政策が、日本の国益を損なわないよう祈るばかりだ。
宗教的にはナイーブな問題であることには変わりない。幸福の科学の「仏法真理」では、魂のきょうだい(人間は基本6人の魂のきょうだいで構成される)には、男女の魂が共存する場合も少なくないという。「仏法真理」を知ることで、今世は自らが選んで、男として、あるいは女として人生修行をしていることを心の拠りどころとしてほしいものだ。
最後に一冊の絵本を紹介したい。オランダで生まれ、すでに9言語に翻訳され世界中で読まれている。タイトルは『王さまと王さま』。あらすじは「ある王国の女王さまが、もう女王としての仕事はうんざりしたという理由で、息子の王子に結婚して王さまになるよう命令する。それを受けて、さまざまな国からお姫さまの候補が募集された。アメリカ、オーストリア、ムンバイ……、お姫さま候補が特技を披露したが、息子の王子にとって誰もしっくりとこない。どうしようかと困っていたとき、召使が「もう一人、マデリーフ姫とお兄さまのハーリック王子です」と紹介する。王子の心はときめいた。「なんて素敵な王子さま」。そう、王子がときめいたのは、マデリーフ姫ではなく、兄のハーリック王子だった。王子さまと王子さまは結婚して、王さまと王さまになったとか。めでたし、めでたし」。LGBTがテーマの絵本で、同性を好きになっても不思議ではないというコンセプトで有名になった。だが、筆者にとって、どうしても結末が納得できなかった。「二人はめでたく結婚しましたが、お世継ぎが生まれず、この国は滅んでしまいました」とさ。おしまい。
〈本文より抜粋〉
オバマ大統領は、大統領選挙での演説や就任演説等で、「ゲイもストレートも、レッド・ステイト(中略)もブルー・ステイト(中略)も、みんな一緒だ!」というような言い方をしました。それには、仏教で言うところの、「色心不二」というか、「善悪不二」というか、「何もかも同じ」という感じがないわけではありません。ただ、そうは言っても、やはり、文明的には下っていく感じが強くあるでしょう。それで、トランプ氏に象徴される「強いアメリカ」「古いアメリカの父親像」といったものが出てきたような気がします。ああいうタイプは、本能的に、「LGBT型の人たちは、国力を弱め、社会の底辺層を拡大する傾向が強い」と見ているのではないでしょうか。(中略)
「平和な時代」が長く続きすぎると、男女の差がほとんどなくなってくるので、ときどき、戦争やさまざまな災害等が起きることがあるのです。そういう意味では、何か、時代を“引き締める役割”が働いているような気がしてなりません。いずれにしても、全体的に退廃の方向に向かうと、文明というのは盛りを越えて衰退していき、やがて、他の文明に呑み込まれていくことになります。したがって、その道を選ぶか選ばないかは、大きな違いになるでしょう。
(PP.97-100)
〈本文より抜粋〉
LGBTについても、しばらく意見は保留しておりましたけれども、どうも先行きはよろしくないという考え方が出てきているし、「心は女だけれども体が男だ」という主張をする人のなかにも、そういう人もいるかもしれないものの、やはり、虚偽、嘘とか、あるいは単なる変態趣味まで入っているので、そこまで擁護しなければいけない理由はないと思います。(中略)女装して、いかにマニキュアを塗って、化粧をして、髪を伸ばして、スカートをはいていても、本人はその権利が欲しいだろうけれども、ほかの女子にとっては、女子トイレに来られたら、やはり恐ろしいものです。(中略)
「心は女性というのは本当か」と思うし、医者だって、これでは信用できないでしょう。そう言っているだけかも分からないわけです。こうしたものには「強度の憑依もある」と私は言っているけれども、それだけではなくて、「“変態”の場合もある」ことはあるので、“変態”でも人間だから擁護はされなければいけない部分はあるものの、やはり、一定以上のことをしたら許されないものもあるとは思います。(中略)したがって、「流れがこうだから」という空気、同調圧力によって、コロナと一緒のように押されることはあるけれども、ちょっと考えて踏みとどまって、おかしいと思うものについては、やはり、そんなにアクセルを踏んではいけません。ちょっと時間をかけて考えてみたほうがいいのではないかと思います。一時期の流行りで止まることもあるからです。
(PP.188-190)
| 企画、構成 編集者プロフィル |
|---|
| 木藤文人(きどうふみと) ジャーナリスト、宗教家。 大学を卒業後、大手広告代理店に勤務。フリーとして独立後、「週刊東洋経済」「プレジデント」「経済界」「ザ・リバティ」等の執筆を経て、2007年、幸福の科学出版に入局。『天国に還るための終活』等、編著も多数。 |
◎メールマガジン『時事メルマガ』は、2025年3月1日から配信を開始しました。※月1回で配信中!
大川隆法著作シリーズから、主に政治、経済等を学べる書籍を紹介して参ります!
ぜひ、購読してみませんか。メールマガジンの登録はこちらへ≫